ジョージ・オーウェル著『一九八四年』を読んで考えたこと、思ったことなどの感想をまとめました。私が読んだのは早川書房の新訳のほうです。
社会学の講義で読むように言われた本でしたが、ぜひ、社会学以外の学問をやっている人にも一読してもらいたい名著です。
この本は主に、監視社会と思想統制が行われている世界が描かれています。
『一九八四年』の書誌情報
- 2009年7月25日 発行
- 2015年8月25日 24刷
- 著者:ジョージ・オーウェル
- 訳者:高橋和久
- 発行所:早川書房
あらすじ
<ビッグ・ブラザー>率いる党が支配する全体主義的近未来。ウィンストン・スミスは真理省記録局に勤務する党員で、歴史の改竄が仕事だった。彼は以前より、完璧な屈従を強いる体制に不満を抱いていた。ある時、奔放な美女ジュリアと恋に落ちたことを契機に、彼は伝説的な裏切り者が組織したと噂される反政府地下活動に惹かれるようになるが……。二十世紀世界文学の最高傑作が新訳版で登場!
『一九八四年』裏表紙より
大まかな設定
『一九八四年』は、大学の講義の課題として購入した本でした。1章だけを読めばよかったので、ゆっくりと読み進めました。
舞台はイギリスで、「党」による支配が蔓延する世界です。
この本の世界では、常にどこかの国(ユーラシアとイースタシア)と戦争をしていることになっており、民衆は戦争に勝利すると喜びます。
しかし、主人公のウィンストンは、戦争に勝利しても喜ぶ描写はありませんでした。彼は、少し前までは別の国と戦争をしていたと「記憶」していたのです。
この作品では、「党」が未来、現在、過去をコントロールしています。ウィンストンが記憶している戦争の相手国の変化も、「党」がなかったことにしているのです。そして、それを何の疑いもなく受け入れることが、この世界においての「正気」な人々であり、ウィンストンにはそれができなかったようです。
また、ウィンストンには、「党」による革命前の記憶が少し残っています。母と妹と三人で過ごしていた記憶が、特に頻繁に作中に出てきます。
しかし、そのような「記憶」があることが、彼が「党」に目をつけられた原因ではないだろうかと思います。
オーウェルが描いたこの世界の『正気』な狂人
オブライエンは、「現実は人間の中だけに存在」していると述べました。
つまり、現実とは、外部に自立して存在しているのではなく、人々の記憶の中にだけ存在しているのです。その人々の記憶は、党の精神を通して見た真実です。党の精神が現実であるのだから、党の精神を通して見た真実は現実である、という論理。
オブライエンは高い知性があるため、反論の余地のない論理でウィンストンに迫ります。
しかし、ウィンストンがまだ正気を保っているとき(オブライエンからしたら「狂気」だが)に、オブライエンのことを狂人だと考えていました。ウィンストンは中途半端に頭が良かったのか、党に染まり切れず、存在するはずもない過去の記憶を持ち、オブライエンを狂人だと思ってしまった。そして、それを隠すことも出来なかったから、オブライエンに目をつけられてしまった。
知性のある狂人は厄介だ。オブライエンは、論理的に、自らの信じている「党」が如何に正しいかを述べます。拷問と共に理詰めの一種の洗脳をされてしまっては、抗うすべもなくウィンストンのようにやがて「正気」になってしまうのでしょう。
愛することと裏切ること
ウィンストンは、最終的に「正気」になってしまったが、かなりの精神の持ち主だと考えます。なぜなら、ギリギリまで(101号室の「ネズミ」の刑まで)ジュリアを裏切らなかったから。裏切らなかったというのは、彼女を自分の身代わりにしようとせずに、愛していたということです。
しかし、結局、ウィンストンにとって一番恐ろしいこと(「ネズミ」の刑)によって、ジュリアを裏切ってしまいました。
最後の章で、ジュリアと再会していますが、何ら特別な感情を抱いていないのが印象的でした。やはり、一度裏切ってしまうと、今までのように「愛する」ことができなくなるのでしょうか。
そして、「ネズミの刑」ってどんな光景なんでしょうね。。。ドラえもんだったら絶叫しそうな名前の刑ですが。
まとめ
この作品は、監視と権力について深く考えさせる作品でした。テレスクリーンも恐ろしいですが、一番恐ろしいのは人間だったと思います。特に、オブライエンのような知性の高い狂人には、どんなに隠していても内なる党への反抗心を見抜かれてしまうのではないでしょうか。
ウィンストンのように「骨抜き」にされた人間は、最後まで「党」という権力の隷従者になるのでしょう。彼は二度と、正気には戻らないのでしょうね。
そして、巻末の附録に、「ニュースピークの諸原理」があります。かなり手の込んだ世界観ですし、なにより言葉を制限されることは思考を奪われるのと同義ですから、恐ろしく思います。
最後に、作品の中でよく出てくる狂気を添えて。
おおきな栗の木の下で―
あーなーたーとーわーたーしー
なーかーよーくー裏切ったー
おおきな栗の木の下で―
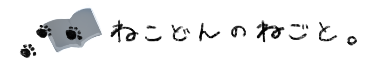


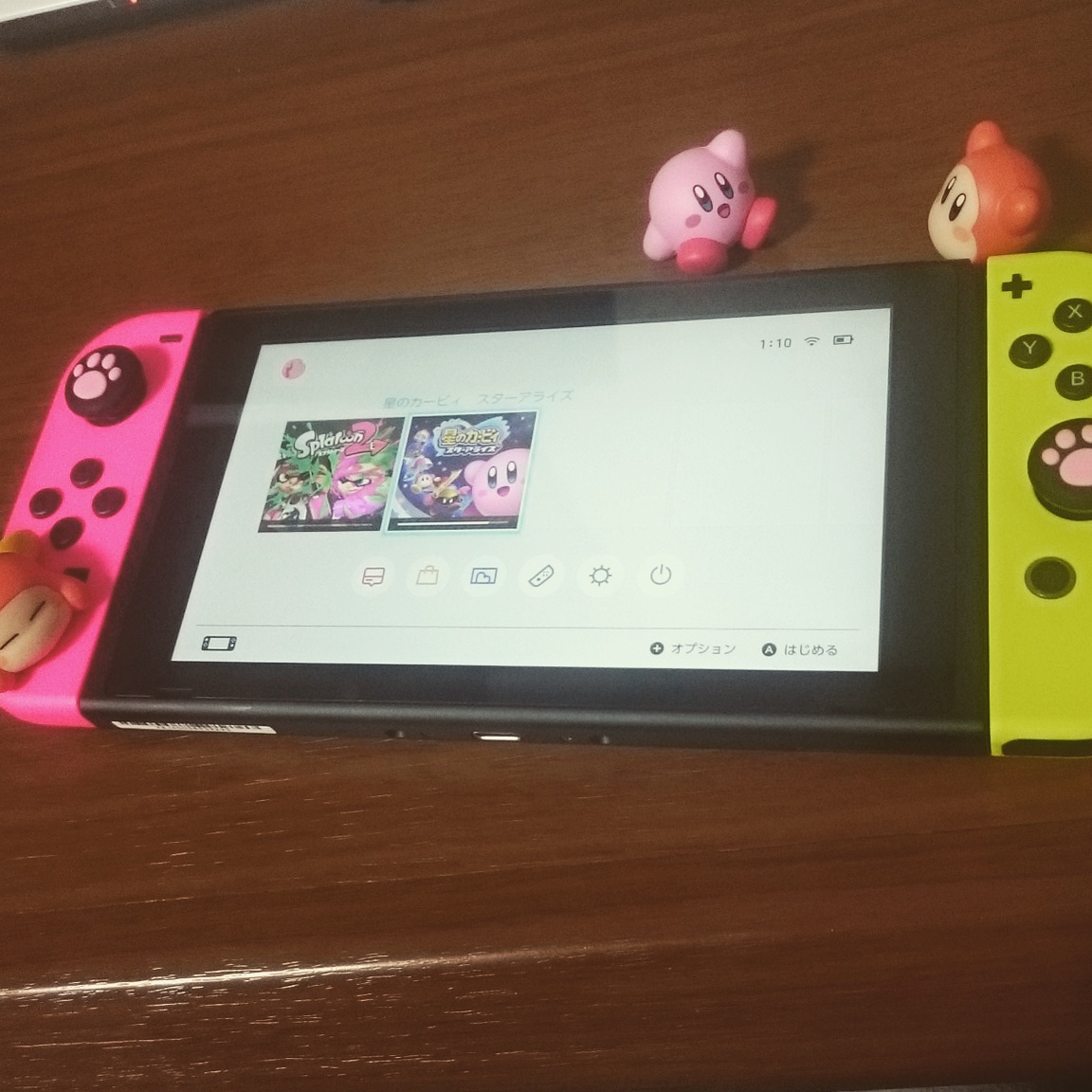
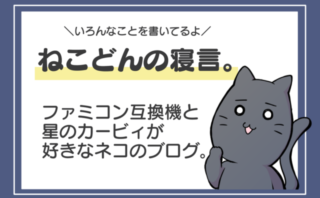
コメント